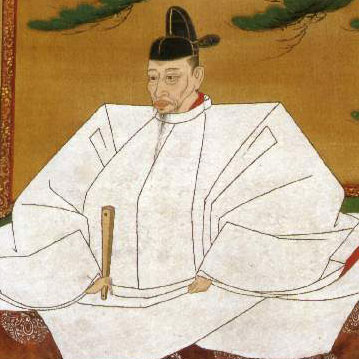秀吉の大軍に対し、粘り強く抵抗する
この時の一益の軍勢は数千規模でしたが、これに対して秀吉は、7万という圧倒的な大軍を動員して伊勢に攻め込んできました。
そして2月の中旬には長島城への攻撃も開始されますが、一益を初めとした滝川勢には優れた武将が多く、頑強な抵抗を見せます。
このため、亀山城が3月まで、峯城は4月まで持ちこたえ、落城後は兵が長島城に集結し、戦闘態勢を維持しました。
一益が粘る間に、勝家は北から秀吉を脅かすべく、2月の末に雪道を切り開いて越前から出陣し、3万の軍勢を率いて北近江に進出します。
このために秀吉は伊勢から撤退しますが、抑えに2万程度の軍勢を残しており、一益は秀吉の軍勢を分散させることに成功しました。
勝家が賤ヶ岳の戦いで敗れる
勝家と秀吉は北近江の賤ヶ岳(しずがたけ)付近で対峙しますが、互いに野戦築城を行って守りを固めたため、戦況が膠着します。
やがて4月になり、美濃で信孝が勝家らの動きに応じて再度挙兵すると、秀吉は三方に敵を抱える情勢となり、信孝を抑えるべく美濃に転進します。
その隙をついて勝家の軍勢が秀吉の前線を崩しますが、秀吉はすばやく北近江に戻り、勝家の先鋒隊を包囲しました。
翌日に決戦となりますが、勝家軍の一翼を担っていた前田利家らの諸将が、突如として戦場を放棄したために陣形が崩れ、勝家の軍勢は壊滅します。
そして勝家は本拠の北ノ庄城に追い詰められ、そこで自害して果てました。
4月末には信孝も追い詰められて自害し、一益はまたも孤立することになってしまいます。
秀吉に降伏し、所領を没収される
一益はそれでもなお、7月まで籠城を続けて孤軍奮闘しますが、ついに力尽きて秀吉に降伏します。
そして北伊勢の所領をすべて没収されたものの、命までは取られませんでした。
一益は剃髪し、織田氏の重臣である丹羽長秀を頼って越前で謹慎することになります。
信長の死から1年もたたないうちに、関東の統括者の地位を失い、領地も失って、信長に仕える以前の、一介の素浪人同然の身分にまで落ちてしまうことになりました。
このあたりの結果を見るに、一益は信長という大きな柱に仕えてこそ力量を発揮できる武将であり、自分自身の目で的確に情勢を見定め、進退を判断するのは、不得手な人物だったのだと思われます。
武将として復帰する
1584年になると、秀吉は織田信雄や徳川家康と対立し、「小牧・長久手の戦い」が勃発します。
この時に一益は秀吉に呼び戻され、武将として復帰し、この戦役に参加することになりました。
織田信雄は伊勢や尾張を領有していたため、この地域で長く戦っていた一益の経験が必要とされたのです。
一益は信雄に味方していた九鬼嘉隆を調略で寝返らせると、6月16日に海上から3千の兵を率い、蟹江浦に上陸しました。
再び蟹江城を奪取する
上陸した一益は、かつて服部友貞を騙して築城させた蟹江城に攻め込んで、これを再び奪取します。
蟹江城は尾張と伊勢の国境付近にあったため、信雄の領地が分断される効果を生み、秀吉は蟹江城を起点として、信雄や家康を討伐する計画を立てました。
これを放置しておくと重大な危機に陥るため、信雄と家康は2日後に2万の軍勢を率いて蟹江城へと攻め込んできます。
この即断こそが、家康が秀吉に敗北しなかったことの、大きな要因となりました。
蟹江城を家康に奪い返される
付近の海上は九鬼嘉隆が守備していましたが、織田・徳川の水軍に攻められて敗北し、蟹江城は海上から封鎖を受けることになります。
その上で、城の大手門が徳川軍の激しい攻撃を受け、6分の1以下の戦力しかない一益の軍勢は、すぐに危機に陥りました。
浪人した後だったので、滝川家の家臣たちは離散しており、このために指揮官級の人材の質が下がっていたことが、一益の抵抗が弱くなったことの原因でした。
それでも一益は長男の一忠や、次男の一時(かずとき)とともに奮戦し、しばし徳川軍の攻勢を防ぎました。
しかし支城の前田城が攻め落とされたことで、これ以上の抗戦は困難となり、一益は和平交渉を行います。
そして7月3日には、織田・徳川軍に城を明け渡して退去しました。
秀吉は7月15日に、6万の大軍を率いて蟹江城へと向かう予定になっていましたが、秀吉にしては珍しく行動が遅く、このために勝機を逸することになりました。
こうして一益は、またしても運に恵まれずに敗れ去りましたが、それでもいくばくかの領地を得て、武将としての身分を取り戻すことになります。
【次のページに続く▼】