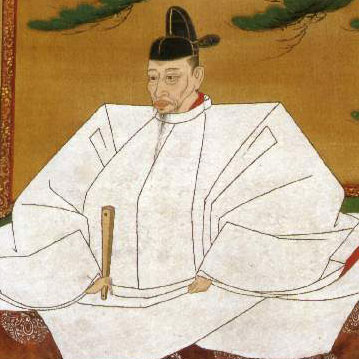秀吉が中央の争いを制し、毛利氏は傘下に入る
中国地方から撤退した秀吉は、急行軍で機内に戻って明智光秀を討ち取り、信長の仇を取ります。
そして織田氏の内部の権力争いによって敵対した柴田勝家をも討ち破り、一躍天下人を狙える地位にまで到達しました。
こうした状況の変化を受けて、毛利氏は秀吉に使者を送って正式に従属することにします。
これによって、毛利氏は独立は失ったものの、120万石という大領を維持し、その勢力を保つことに成功しています。
隆景らは、元就の遺言の達成に成功したと言えるでしょう。
なお、この時に隆景は、養子に迎えていた甥の小早川秀包を、人質として秀吉に差し出しています。
隆景は妻との関係は良好でしたが、子を得ることができなかったため、一族から養子をとっていました。
伊予に攻め込む
秀吉は敵対した徳川家康や織田信雄らと小牧・長久手で戦い、局地戦に敗れたものの、全体としては優勢を保ってこの戦役を終えました。
そして家康と結託し、秀吉に敵対した地方勢力の討伐を行い、四国の覇者であった長宗我部元親とも戦うことになります。
秀吉は弟の秀長を総大将とした10万の大軍を四国に派兵し、毛利氏にも伊予からの侵攻を命じました。
これを受けて輝元は3万の軍勢を動員し、元親に味方する伊予の勢力を攻撃します。
この時に隆景は第一陣として伊予に乗り込み、金子元宅という伊予の中核をなす武将を討ち取ります。
これによって抵抗が弱まり、毛利軍は2ヶ月程度の戦いで伊予全土を掌握しました。
一方で豊臣軍も順調に長宗我部軍を打ち破り、これを降伏させています。
この頃に秀吉は朝廷から豊臣の姓を与えられ、関白にも就任し、天下人としての地位を確立させました。
独立した大名に立てられそうになるも、毛利家臣の立場を保つ
秀吉は各地の大名の家臣の中から、特に優れた者を直臣として引き抜く措置を取っていました。
これはその大名家の力を弱らせつつ、豊臣氏の力を強めるための政策でした。
これに隆景も選ばれ、四国征伐が成功した後に、伊予一国を与えた上で、独立した大名として取り立てたい、と秀吉に告げられます。
しかし隆景は毛利氏の家臣であり続けることにこだわり、毛利氏に伊予が与えられた後で、自分にそれが授けられる、という形をとることで、身分をそのままに据え置いています。
隆景はあくまでも毛利氏を忠実に支えることを本望としており、野心を抱いて自分の身分を引き上げることは望んでいませんでした。
伊予の統治で称賛を受ける
こうして隆景は伊予の領主となり、配下の武将や養子の秀包らを主要な城に配置し、統治を開始しています。
戦いによって征服された土地では、統治の初期に強い抵抗を受けることが多いのですが、隆景は巧みに伊予を治めることに成功し、一度も反乱を起こされませんでした。
隆景は「長く思案して遅く決断する。分別の肝要は仁愛であり、仁愛に基づいて判断をすれば、もしも思慮が外れたとしても、そう大きな間違いは起こらない」といった言葉を遺しています。
伊予の統治においても、熟考してから決断を降し、降伏させた領主たちに仁愛を旨とした態度で接したため、反乱を起こされることがなかったのでしょう。
似たような事例では、黒田官兵衛が豊前(福岡県)で反乱を起こされて鎮圧に苦労し、佐々成政が肥後(熊本県)の統治に失敗して自害させられていますが、彼らとは対照的な結果を作り出しています。
黒田官兵衛も佐々成政も優れた武将たちでしたので、その能力が劣っていたというよりも、隆景が特別に優れていたと見るのが妥当でしょう。
こうして伊予の統治で実績を示した隆景は賞賛され、秀吉からさらに厚い信任を受けるようになっていきます。
隆景は軍事にも統治にも熟達しており、その気になれば、独立した大名としても十分にやっていけたでしょう。
【次のページに続く▼】