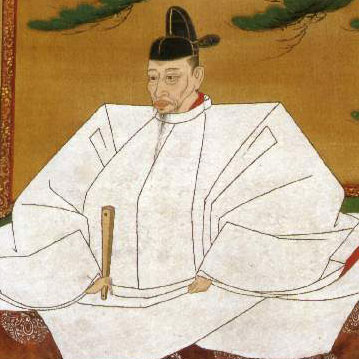尾張の状況
義元の勢力は、桶狭間の戦い以前にも尾張に浸透しており、東部の要衝である鳴海城や沓掛城、大高城などを手中に収めていました。
これに対し、信長は大高城を孤立させるべく、丸根・鷲津の両砦を築き、他の今川方の城との連携を断っていました。
この影響で、大高城は慢性的に兵糧不足となり、三河衆が敵中を突破して物資を運ぶ役目を果たすなどしています。
ですので、義元は戦略の初期段階として、大高城の安全を確保するため、丸根、鷲津砦を攻め落とすことを目指します。
そうして東部の支配を確実にしてから、尾張の中央部にも攻め込み、信長を滅ぼさんとしていたのだと思われます。

部隊の配置
義元は丸根砦の攻略を、松平元康(後の徳川家康)が率いる三河衆・2千5百の軍勢に命じました。
また、鷲津砦は朝比奈泰朝が率いる遠江衆・2千に攻略を命じます。
こちらには三浦備後守が率いる3千の援軍も付与しています。
いずれも最前線では三河と遠江という、属国の兵を戦わせていますが、これが今川氏の常套手段でした。
属国の兵に最も厳しい戦場で戦わせ、損害を引き受けさせ、本国の兵はその果実を受け取る。
そのようなことを繰り返すうちに、駿河衆はだんだんと弱体化していったようです。
一方で、三河衆は長年に渡り、尾張侵攻の尖兵として義元に酷使されていましたが、それがかえって、三河衆を強兵に育て上げる結果を生み出しました。
このことが後に、元康が勢力を伸ばすための基盤として機能することになります。
義元は鳴海城に岡部元信を配置して防備を固めると、葛山信貞ら5千に、信長の本拠地である清洲城方面を担当させます。
また、自らも5千の兵を率い、本軍として沓掛城に帯陣し、全体の指揮にあたりました。
これに対し、信長は総勢で5千の軍勢しかもっておらず、今川軍の一部隊と戦うのがやっと、という状況でした。
このため、まともに戦えばまず勝ち目はなく、信長が取れる戦術は、ごく限られていました。
戦いの主導権は義元が握っており、信長は受けて立つ立場だったのだと言えます。
戦いの始まり
義元は1560年の5月19日に、総攻撃を開始させました。
これを受け、松平元康は早朝から丸根砦への攻撃を行います。
砦を守るのは織田方の勇将・佐久間盛重で、兵は少ないながらも、よく防戦に努めました。
松平軍の武将、松平正親、政忠らを討ち取り、一度はその攻勢をはねのけています。
信長が最前線に配置するだけのことはあり、守備兵は三河衆に負けぬほど精強だったようです。
そして武将を討ち取られた松平軍が動揺を見せると、その隙をつくべく、佐久間盛重は城門を開いて打って出ました。
これを見た元康は、その勢いを避けるべくいったんは後退し、弓矢や銃撃を浴びせて打撃を与えます。
すると盛重に銃弾が命中し、彼はあえなく戦死してしまいました。
主将が討たれ、守備兵が崩れ立つ隙を見逃さず、松平軍は猛攻をかけて城門を突破し、丸根砦の攻略に成功しました。
この時、元康はまだ18才でしたが、すでに堂々たる指揮能力を備えていたことがわかります。
元康は敵将7名の首級を義元に送り、戦功を称賛されました。
そして義元は、通路の打開がなった大高城に入って休養を取るようにと、元康に命じています。
【次のページに続く▼】