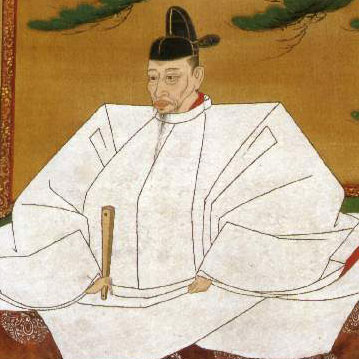各地での戦い
この戦いは尾張・伊勢方面だけでなく、日本の各地で展開される広域戦となりました。
紀州の雑賀・根来衆が家康に味方し、摂津の岸和田城に攻め込んできますが、秀吉配下の中村一氏がこれを守りきっています。
秀吉はこの報告を受けていったん大坂に帰還しています。
また、四国の長宗我部元親が讃岐(香川県)を制し、家康の要請を受けて摂津や播磨を攻撃する姿勢を見せ、これに対処する必要もあり、秀吉はしばらく大坂に滞陣することになります。
北陸では家康に味方した佐々成政が、前田利家が守る加賀(石川県)へ1万5千の大軍を率いて攻め込みます。
しかし末森城付近で利家が3千程度の部隊で奇襲をかけ、成政を撃退し、この侵攻を防いでいます。
関東でも家康についた北条氏が、秀吉についた佐竹氏と戦うなどしており、関ヶ原の戦いほどではないものの、天下分け目と言ってもいいほどの規模に戦域が拡大していました。
全体として見れば、10万というまとまりのある戦力を保有する秀吉方が、優位に戦況を進めていきます。
信雄との和睦
開戦から半年ほどが過ぎると、信雄の陣営では疲弊の色が濃くなっていました。
滞陣が長引くにつれて戦費はかさむものの、尾張や伊勢の領国が秀吉方に占拠されて収入が落ち込んでいたためです。
このため、信雄はこれ以上の抗戦をあきらめ、伊賀と伊勢の半分を秀吉に割譲することで和睦を成立させます。
これは同盟相手である家康には無断で決定されてしまい、家康ははしごを外されるかっこうになりました。
信雄が和睦してしまうと、秀吉と戦う大義名分も戦力も失うことになり、さしもの家康も、これ以上戦い続けるのは難しくなりました。
こうして家康は局地戦では勝利したものの、最終的には秀吉と不利な条件で和睦をすることになってしまいます。
戦術では勝ったものの、戦略に敗れたことになり、家康は秀吉の勢力の巨大さを思い知らされることになりました。
家康は領地こそ譲らなかったものの、次男の於義丸を秀吉の養子、つまりは人質として差し出しており、実質的にこの戦役は秀吉の勝利に終わっています。
しかし秀吉の4分の1程度の戦力でありながらも、直接の戦いでは引けを取らなかったことから、家康の存在感が増していくことになりました。
秀吉も家康は力でねじ伏せるよりも、懐柔して自分の勢力に取り込んだ方がよいだろうと考え始めます。
秀吉には天下を全て自分の手で握ろうという意図はなく、各地の有力者を取り込むことで、早期にそれを成し遂げようと企図していました。
それが短期間での天下統一を秀吉に成し遂げさせますが、一方で室町幕府に類似した、政権基盤の脆弱さにもつながっていくことになります。
紀州征伐
紀州は雑賀衆や根来衆といった傭兵部隊の根拠地で、この時は家康の勧誘を受けて秀吉と戦っていました。
雑賀衆らは一向宗を信仰していたことから、信長の時代にも石山本願寺に味方して戦っており、十数年に渡って織田・羽柴軍に抵抗していたことになります。
しかしもはや石山本願寺はなく、周囲に連携できる勢力もなく、紀州は孤立した状態に置かれていました。
秀吉は和睦交渉をするものの、これが決裂したことから、1585年の3月に10万という大軍を紀州に送り込み、雑賀衆や根来衆の殲滅を図ります。
これに対し、雑賀衆らの戦力は1万5千程度でした。
紀州は鉄砲の産地であり、雑賀衆らは多数の鉄砲を装備し、その操作に熟練しています。
このため、秀吉軍は苦戦を強いられ、雑賀衆の前線基地である千石堀城を攻略するのに1000人もの死傷者を出しています。
しかし数では圧倒的に勝っていたため、波状攻撃をしかけて強引にこれを討ち破っています。
秀吉は城に篭もる人員を、非戦闘員も含めて殲滅するように命じ、皆殺しにしています。
羽柴軍は損害を恐れずに激しい攻撃を繰り広げ、わずか3日ほどで雑賀衆の前線基地を崩壊させました。
これによって雑賀衆は混乱に陥り、中には秀吉方に寝返る者も出て、自滅するようにしてその勢力が衰退していきます。
【次のページに続く▼】